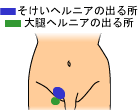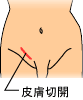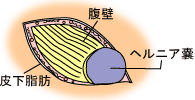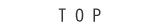| ヘルニアとは脱出するという意味です。一般消化器外科では脱出する臓器が腸であることが多いので脱腸とも言います。放置するとかん頓といって脱出した臓器がもとに戻り難くなり血行障害をきたして壊死になることがあり、緊急手術が必要な事があります。治療を行うのは下記の疾患です。 | ||||
| 臍ヘルニア: いわゆるでべそです。 腹壁瘢痕ヘルニア: 過去の手術創の一部からでる脱腸です。術後の年数は関係ありません。 内ヘルニア(閉鎖孔ヘルニアなど): 腹腔内の一部に腸がはまりこむために腸閉塞となります。 そけいヘルニア: 一般に脱腸と呼ばれるもので、そけい部(下腹から陰部の腫れ)で認められます。 大腿ヘルニア: お腹の中のものが大腿部の前面に出てくるものをいいます。 |
||||
| ■外そけい(間接)ヘルニア お腹などから内そけい輪を通って、小腸などが出てきます。そけいヘルニアの多くはこの外そけいヘルニアです。身体の右側に多く見られる傾向があります。内そけい輪から男性では精索が女性では子宮靭帯がお腹からでてきます。 |
||||
|
||||
| 症状 立ち上がったり、お腹に力を入れると足の付け根(そけい部)が膨らみ、男性の場合大きなものでは陰嚢まで達するものもあります。こぶ状の膨らみやしこりは体を横にしたり、手で押さえると消えることがあります。腸が出たり入ったりしている際は、軽い痛みやつっぱり、便秘が起きる程度で、強い痛みなど特別な症状はありません。飛び出したまま戻らない場合(かんとん状態)は緊急手術が必要になります。 原因 子供では生まれつきのものが多く見られますが、大人はそけい部の組織が年をとるにつれ弱くなることが原因になります。 このような手術法があります そけい部手術:足の付け根の所を6〜8cmほど切開して行います。昔から行われている方法はヘルニアの袋を(ヘルニア嚢)を根元でしばった後に、腹壁の筋肉を縫い合わせてヘルニアの出口をふさぐ事により、ヘルニアの再発を防ごうとするものです。この方法では手術後、足の付け根のつっぱり感がしばらく続くのが難点です。また年をとるとともにさらに筋肉が弱くなり、ヘルニアが再び起こったりします。最近、ヘルニアの出口をふさぐとともに腹壁の補強ができる人工の補強材を使った手術が行われるようになりました。この方法では腹壁が弱くなってきても人工材の補強があるので手術後のヘルニア再発率が起こりにくくなります。(再発率1%未満)。手術は半身麻酔以外にも局所的な麻酔でもでき、短時間(1時間以内)で終わります。また、手術後の痛みなどが少なく、入院期間も短くてすみ、早くもとの生活に戻る事ができるなどの長所も持っています。 手術の流れ 1、手術前に気をつけたいこと:血液や心電図などの検査を行います。その後、ひとりひとりの患者さんに応じた治療を決めるために診断を行いますので、他の病気を治療したり、薬を飲んでいる患者さんは申し出てください。また、指定された時間から飲食が止められますが、これは手術の安全に関わることなので守って下さい。 2、麻酔:原則として腰椎麻酔、または硬膜外麻酔という半身を麻酔する方法で行います。これらの方法は全身の麻酔と違って、手術をする場所の感覚を取るだけで、患者さんの意識にはあまり影響がありません。またこのような麻酔では、リラックスして手術が受けられるような薬を使用する場合もあります。
|
||||
| 4、.ヘルニア嚢の処理: ヘルニア嚢を他の組織と分けた後少し切開し、内容物(小腸など)をお腹の中に戻します。次に、ヘルニア嚢を根元でしばった後切除し、端をお腹に戻します。 | 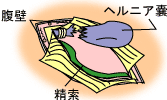 |
|||
| 5、.周辺組織の補強メッシュによる補強: ヘルニアが再び出てこないように、弱くなった所に人工補強材をはめこみます。人工補強材はヘルニアの出口をふさぐとともにお腹の内側の平面を覆い、弱くなった組織を補強します。補強材は柔らかいメッシュ状のシートで身体に害が無いといわれている人工の素材で作られています。手術後のつっぱり感や痛み、再発が少ないことが特徴です。 | ||||
| ※この病気の説明を音声でもお聞き頂く事ができます。 | ||||